カラムシ栽培におけるコガヤ(カリヤス)の重要性
菅家博昭
ボーガヤ(植物和名ススキ)とコガヤ(植物和名カリヤス)。形状は似ているが、異なる植物として認識され福島県奥会津の昭和村では古くからそれぞれに暮らしのなかにおいて利用されてきた。
イネ科のススキ属Miscanthus Anderssonには3種類ある。ススキMiscanthus sinensis Andersson、オギMiscanthus sacchariflorus、カリヤスMiscanthus tinctorius。いずれも昭和村で現在も生育が確認されている。
特にカリヤスは岐阜県富山県を中心とする中部山地に分布は濃く、東北地方南部までが分布域である。ススキに比べ桿が細く刈りやすく、合掌作りの屋根に、ススキ(大萱)とともにカリヤス(小萱)も使われる。その理由はススキよりも長持ちする、という。富山県五箇荘ではカリヤスが屋根材に使われているが、近年身近なススキから、かつての屋根材カリヤスを要望する事例が茅葺き保存家屋の改修時に、出て来ている(※1)。
カリヤスは、昭和村ではコガヤと呼ばれている。ススキはボーガヤである。ボーガヤは棒茅の意だと思われ昭和村域では使用されているが大茅と呼ぶ地域も隣接の柳津町冑中等にはある。中部山岳地域も大茅・小茅と呼んでいる。異なる植物として、明確に分けている。
昭和村で「カヤバ(カヤカリバ)」とは、共有利用を前提として採取制限(禁止)を持ち、春の山焼きが行われ、秋彼岸以降に、やまのくちあけ(山の口、鎌揃え)で開放・採取開始する、コガヤ(カリヤス)を刈る半自然草地のことである。これらは第2次大戦前後まで昭和村内の全域(各集落)で、行われていた。集落を取り囲む山塊のなかに複数設置されている。
カヤバの春の山焼きは、残雪が尾根筋に残る時期に前年の草類が乾燥して燃えやすい時期に、斜面下方から火を点火し、そのままに放置するもので「くっつげはなし」(松山 ※2)とよばれていた。火は消さず自然鎮火を待つため数日から1週間も燃え、時に尾根を越えて隣村の山まで焼けたことがある、という(大芦)。
コガヤを刈る時期は旧暦の秋彼岸後で、水田での稲刈り等との関係で採取(刈り取り)時期が集落毎に決められていた。すでに立ち枯れし乾燥が進んでいることもあるが、3把(は、束)で立てさらに3把重ねての6把立が多く、それで乾燥させる。カヤマキ、カヤボッチはタテ(立)で数える。乾燥後、それを集落に運搬した。
晩秋、集落のなかの家屋(母屋)外壁にはコガヤを2段、3段に巻き、フユガキ(冬囲い・雪囲い)とした。春先に飼育動物(馬牛等)の餌が無くなると、このフユガキを外して与えることもあった。土蔵等にはボーガヤ(ススキ)をフユガキとして、これは外しながら木炭を入れるスゴを編んだ(大岐)。
これまで現代語訳の筆耕が存在していたが、喜多方市立図書館蔵で、喜多方市教育委員会の協力でその原本がはじめて今回の「からむし畑」展の事前調査で確認された。安政五年(1858)に松山村(現在の昭和村大字松山)の佐々木志摩之助が書いた「青苧仕法書上」という近世江戸時代のカラムシ栽培の手引き書で、ほぼ現在に伝わる内容と同じであることを証左している。特に秋にカヤを刈り、家の冬囲いとし来春そのカヤでカラムシ(青苧)を焼くということも明記されている。
フユガキのコガヤは、カラムシ畑に運ばれ、焼き草として畑に散らし(掛けて)焼かれる。焼畑のときの、コガヤの火力がカラムシの芽を揃える、品質確保のためには必要なものであったようだ。コガヤでなければならない理由の今後の聞き取り調査が待たれる。カラムシ畑を焼くには、ボーガヤだと火力が強い、あるいは太くて燃えないなどの問題がある(小中津川)。
2010年9月17日(金)雨の午前、昭和村小中津川の柳沢で、本名初好さん(昭和13年生)が茅刈りをしていたので、話をうかがった。四畝歩のカラムシ畑を春に焼くためのカヤ(ススキ)の調達をしている。コガヤ(カリヤス)は少なくなり、ボーガヤ(ススキ)を刈っている。左手で三つかみで1束とし1把(いっぱ)。それを3把で立てて、上に3把を重ねる。1立(ひとたて)は6把(ろっぱ)立て。これを30立(たて)、昨年(2009年)秋に刈って乾燥させ、翌春(つまりこの春5月)に、焼草とした。茎が太いと燃えないから根本から50cmくらいは切り捨て、残った上部のみ使っているという。
4畝(アール・a)のカラムシ焼に必要なカヤは、30立て。180把である、ということが明らかになった。本来はコガヤ(植物和名カリヤス)が良いがいまは少ない。
さて、カヤバの管理は、どのようにしたのか?といえば、「秋にコガヤを刈るときに手入れした」といい、その内容は「生えてきた樹木を根本から切り、不要な草類も刈り、そこに置いた」という管理であった(大岐)。
「コガヤはカヤバの周囲の樹木が育ち日陰になると消え」「ボーガヤに負けて株が無くなる」という。「肥えた土地にはボーガヤが育ち、やせた硬い土のところにはコガヤが育つ」といい「コガヤのカヤバにはシメジもよく出る」という(大岐)。カヤバは春の山菜であるワラビも多く出、また夏の盆にはボンバナと称するオミナエシ、ワレモコウ、キキョウなどの野の花が採取され仏前・墓前に手向けられた。
昭和村における草の利用は馬の飼育のための秣(まぐさ)、いわゆる朝草刈り、冬の飼育飼料としてのカッタテ・カッポシ(乾燥草)を草のショウ(生)が抜ける前の秋彼岸前に刈る。そして屋根材のボーガヤ確保、フユガキとカラムシ焼き・屋根の補修のサシガヤとしてのコガヤの刈り取り、、、と目的に応じた草の確保、半自然草地の維持管理が行われていた。しかしその具体的な内実はしられていない。稲刈り後、稲束をネリ(稲架)で乾燥する。その際の最上段は「カサイネ(笠稲)」と呼び、湿気が最後まで抜けないため別に管理する。このカサイネをカラムシ畑のほとりに運ぶ(カサワラ)。カラムシ焼き畑後に散らすしきわらとして湿気具合、風で飛ばないなど使いやすいのだ、という(大岐、大芦)。
昭和村におけるカラムシ栽培・青苧生産については、それを支える広大なカヤバ(カリヤス草地)の存在。植物、特に多用な草ヒロロ(ミヤマカンスゲ)や蔓のマタタビ、モワダ(シナ)等樹皮を維持管理し、それを生活の中で活用してきた。その基層文化、生活技術、自然認識のうえに、カラムシ栽培・生産が形成されている。カラムシ単独では持続はあり得ず、その全体像を明らかにすることと、カラムシにつながる生活技術を復権するひとつの試みとして、たとえば遊休農地等にコガヤ(カリヤス)を生産する小茅畑の復活が待たれる。
また近年、減農薬農業を政府が推進しているが、そのなかの技術にバンカープランツがある。目的とする植物(野菜等)の園地をトウモロコシ等の背の高い植物等で帯状に周囲を取り囲む。このことで囲う植物帯で侵入する昆虫等を遮蔽し、あるいは遮蔽帯に小さな生態系を作り、この囲い植物帯から園地に益虫を供給する、という農法。これはかつて昭和村域でアサとカラムシの栽培が行われていた時代の、カラムシ畑をアサで囲む技法に似ている。風除けとしてのアサの利用であるが、昆虫への対応など、このような伝統技術の現代的解明も今後必要になっている。「ウセクチ」のカラムシ畑にアサを蒔く、という連作障害回避技術解明も含めて、現在の「からむし畑」の技術解明課題は多い。カラムシ生産など伝統農法が内包している哲学的認識、伝統農法技術の科学的解明は、第三世界の支援に援用されるだけでなく、日本の山間地域の基層文化の再生を通し次世代の成熟のために必要となってくると思われる。(かんけひろあき 昭和村大岐在住、会津学研究会代表)
-----
(※1)2010年10月7日、大芦家で開催された会津学研究会主催「コガヤに学ぶ」で報告した柏春菜さん「地域毎の半自然草地維持の仕組みとそのバックグラウンドについて」(岐阜県立森林文化アカデミー森と木のクリエーター科里山研究会)による。
(※2) 『福島県立博物館紀要』第20号(2006年)に、鈴木克彦さんが「昭和村松山物語~2005年の聞書から」を報告している。このなかで「くっつげ放(はな)し」(87ページ)、「カッチギ(刈敷)」「カッポシ(刈り干し)」(92ページ)についての記載がある。カッチギについては雑木の枝を切り積み翌年使用する、とある。
skip to main |
skip to sidebar
→→会津学6号 2010年11月14日、発刊
→→会津学3号(奥会津書房) 2007年

朝日新聞福島版に3年連載したもの

特集:暮らしを編む

2008年刊、山に生きる

2007年刊、植物に添う
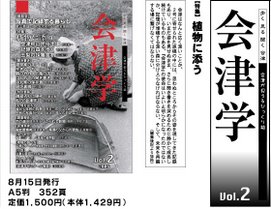
2006年8月発行

2005年創刊号。現在増刷5月14日出来。
Twitter
事務局は〒969-7511 福島県大沼郡三島町宮下字中乙田979 奥会津書房。電話0241-52-3580、ファクス3581
twitter aizugaku
■2015年3月15日 最終巻
■雑誌『会津学』は2005年に創刊し、現在まで毎年8月に1冊ずつ、これまで6冊を刊行。その最新号は2010年11月に6号を発刊しましたが、第7号の編集は2011年3月11日の震災で中断しています。ようやく2015年3月15日に最終巻として第7号を発刊しました。聞き書きを方法として会津地方の人びとの暮らしや生き方を学んでいます。
2011年11月21日(日)13時に福島県三島町西方・西隆寺で『会津学6号』発刊集会を開催しました。
福島県内で読者会を計画しています。主催者を募集しています。会津学研究会の代表菅家博昭と、奥会津書房の編集長の遠藤由美子の2名で、あなたの住む街で2時間ほど対話をしたいと思っています。第1号~6号まで、本を持参して、この本の記事や、その後連関して生まれた子供の聞き書きなど、エピソードをお伝えしたいと思います。
■2011年1月31日午後には只見町にて奥会津大学1期「地域の調べ方」として3時間話しました。pdfチラシ→ 奥会津大学
福島県内で読者会を計画しています。主催者を募集しています。会津学研究会の代表菅家博昭と、奥会津書房の編集長の遠藤由美子の2名で、あなたの住む街で2時間ほど対話をしたいと思っています。第1号~6号まで、本を持参して、この本の記事や、その後連関して生まれた子供の聞き書きなど、エピソードをお伝えしたいと思います。
■2011年1月31日午後には只見町にて奥会津大学1期「地域の調べ方」として3時間話しました。pdfチラシ→ 奥会津大学
2011年7月30日、奥会津大学2期「地域の調べ方」は昭和村下中津川でのフィールド・ワーク、午後に昭和村公民館で座学を行いました。
2012年6月20日、奥会津大学3期「地域の調べ方」では、昭和村大字小野川字大岐集落のフィールド・ワーク(暮らしの風景・生業複合の歩み)と、午後に昭和村公民館の座学(小さな暮らしが結ぶ外の世界)を予定しています。講座運営事務局は苧麻倶楽部(昭和村下中津川)。
→→会津学6号 2010年11月14日、発刊
→→会津学3号(奥会津書房) 2007年
会津物語 2015年8月刊

朝日新聞福島版に3年連載したもの
会津学6号(2011年11月刊)

特集:暮らしを編む
身近な人びとから学ぶ「会津学」
福島県立博物館の公開講座
■2012年4月19日より会津若松市内の福島県立博物館の赤坂憲雄館長の木曜のひろばは新テーマ『老媼茶話』で開催。午後1時30分より。開催日は、 5月17日、6月21日、7月19日、8月16日、10月18日、11月15日、12月13日、2013年1月17日、2月21日、3月14日
■2011年の赤坂館長の講座は「遠野物語を読む」。311地震のため震災関連の内容となったこともあった。
■2010年3月4日(木)13時30分から、「会津学農書」の講座となります。最終回は「会津農書」と「会津の三泣き」。赤坂憲雄館長、佐々木長生学芸員の最終講義(定年退職される)。
→→ 福島県立博物館
会津農書』は貞享元年(1684)に佐瀬与次右衛門によって著述された農業技術書。与次右衛門の経験と旧慣習に基づく、中世から近世初期にかけての会津の民俗が記されています。
■ 2月13日 午後1時30分。民俗講座(視聴覚室) 佐々木長生と民俗を語る。鈴木克彦さん。「奥会津 山村の暮らしと民俗」。3月13日、榎陽介さん。
→→ 福島県立博物館
会津農書』は貞享元年(1684)に佐瀬与次右衛門によって著述された農業技術書。与次右衛門の経験と旧慣習に基づく、中世から近世初期にかけての会津の民俗が記されています。
■ 2月13日 午後1時30分。民俗講座(視聴覚室) 佐々木長生と民俗を語る。鈴木克彦さん。「奥会津 山村の暮らしと民俗」。3月13日、榎陽介さん。
会津学4号(発売中)

2008年刊、山に生きる
会津学3号(発売中)

2007年刊、植物に添う
会津学2号(発売中)
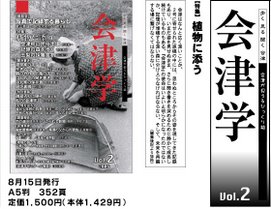
2006年8月発行
『会津学』の発刊と研究会発足
『東北学』に代表される地域に学ぶ作業を提唱している赤坂憲雄さんが2003年4月に会津若松市の福島県立博物館長に着任されました。奥会津書房では、2004年4月に昭和村で懇談会を開き、その後、地域の人々が20名集まり、同年10月に三島町ふるさと荘で会津学研究会は発足しました。10年間の活動を予定しています。 地域の人びとから聞き書きによる方法で教えていただいたことを語り手の許しを得て編集・出版しています。2005年8月に『会津学』創刊号を出版。以後、毎年夏のお盆(8月15日)に年1冊刊行を目標として2008年夏、4号まで300ページの本を出版しています。地域の人々の暮らしに学ぶ地域誌です。
このウェブページの編集は菅家博昭が担当しています(2007年5月1日設置、5月7日改訂)。
このウェブページの編集は菅家博昭が担当しています(2007年5月1日設置、5月7日改訂)。
関係先名簿
会津学1号(増刷、発売中)

2005年創刊号。現在増刷5月14日出来。
編集者紹介
- 菅家博昭
- 日々の記録。

