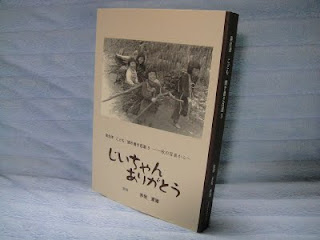2011年5月26日(木)10:35より
福島県立川口高校:奥会津風土体感プログラム(資料)
昭和村大岐 菅家博昭
1.地域(集落・大字、むかしの村)、流域、峠
2.調査(調べ方)
フィールドワーク(野外調査)
聞き書き(聞き取り調査→編集し成文化する)
文献調査
3.「山が、へ(減)るほど、ある(歩)いた」
共生、持続可能性(サスティナビリティ)など無い
4.調査の限界(聞く人の枠)
考え方:全体を見て、言葉にこだわる
言葉→もの、おこない(行為)の表現を支える哲学(考え方)を探る
5.からむし焼き(青苧焼き)→「発音」「過去の作業者の日記」「文献」→作業目的を言い当てる
6.ぜんまいおり(ぜんまい折り)→行為による環境保全と伝承
7.すぎっぱひろい(杉葉拾い)→
8.きのはさらい(木の葉さらい)→落ち葉ではなく、なぜ木の葉なのか?
9.土地の呼び名(地名、俗称)からその地域の人間の行動範囲を探る→記憶を呼び出す
10.自分史とライフワーク、地域誌(集落誌、字誌)と地域文化
11.暮らしを支える基層文化と技術、産業
12.からむしとアサの輪作技法。バンカープランツとしての技術
13.青苧(あおそ・からむし)という鮮度と品質を表現した呼び名
14.かすみ草の世界
15.春木山、薪炭林、里山、コナラの萌芽更新(たてたてぎり)、雪の利用
2011年5月25日水曜日
2011年4月19日火曜日
会津図書館の移転・開館(4月17日)
■会津若松市栄町3-50の市民会館・中央公民館跡地に『生涯学習総合センター(会津稽古堂)』が4月17日に開館した。2階が会津図書館。これまで城東町の福島県立博物館脇にあった図書館が、新装開館して、郷土資料等がたいへん調べやすくなっている。
→ 会津若松市立 会津図書館
→ 会津若松市立 会津図書館
2011年4月18日月曜日
4月17日(日)15時、西隆寺にて定例会
■2011年4月17日(日)15時より、奥会津・三島町西方の西隆寺にて、会津学研究会の定例会を開催いたしました。3月11日発生の東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所の事故(放射性物質の拡散)について話し合いをしました。1ヶ月に発刊された朝日・毎日・読売・日経・産経・民報・民友新聞の記事のクリッピング24ページを資料としました。
■4月14日に首相官邸で開催された「復興構想会議」に、佐藤雄平福島県知事・玄侑宗久和尚・赤坂憲雄福島県立博物館長(学習院大教授)が委員として参加し、原発事故も合わせて議論するよう要請しています。
■雑誌『会津学』は2011年に第7号を夏秋に発刊する予定でしたが、大震災を受け、編集方針の見直しをしています。2011年の発刊は見送り、2012年以降に発行することを確認致しました。
■3月20日に予定していた「子ども聞き書き発表会」は震災のため中止となりました。ただ報告書は予定通り発刊しています(第3号)。
■地震より1ヶ月、震度5近い余震も頻繁に発生しています。
■4月14日に首相官邸で開催された「復興構想会議」に、佐藤雄平福島県知事・玄侑宗久和尚・赤坂憲雄福島県立博物館長(学習院大教授)が委員として参加し、原発事故も合わせて議論するよう要請しています。
■雑誌『会津学』は2011年に第7号を夏秋に発刊する予定でしたが、大震災を受け、編集方針の見直しをしています。2011年の発刊は見送り、2012年以降に発行することを確認致しました。
■3月20日に予定していた「子ども聞き書き発表会」は震災のため中止となりました。ただ報告書は予定通り発刊しています(第3号)。
■地震より1ヶ月、震度5近い余震も頻繁に発生しています。
2011年3月31日木曜日
鹿児島県での会合は1年延期へ
■2011年3月30日。
会津学研究会、鹿児島県沖永良部島での開催と継続して交流が続いていました次回大会は本年11月初旬に鹿児島県内の志布志市で弥五郎祭り時に開催する予定でしたが、3月11日の東北地方太平洋沖地震(政府は4月1日に東日本大震災と命名)が発生し、福島県浜通りに建設されてある東京電力第一発電所の事故(3月15日放射性物質の放出)のため、来年(2012年)開催へと延期となりました。これまで開催準備を進めておられた、鹿児島民俗学会の所崎平先生にはたいへんご心配をおかけしました。
会津学研究会、鹿児島県沖永良部島での開催と継続して交流が続いていました次回大会は本年11月初旬に鹿児島県内の志布志市で弥五郎祭り時に開催する予定でしたが、3月11日の東北地方太平洋沖地震(政府は4月1日に東日本大震災と命名)が発生し、福島県浜通りに建設されてある東京電力第一発電所の事故(3月15日放射性物質の放出)のため、来年(2012年)開催へと延期となりました。これまで開催準備を進めておられた、鹿児島民俗学会の所崎平先生にはたいへんご心配をおかけしました。
2011年1月31日月曜日
地域の調べ方・講座
■2011年1月31日(月)13~16時、福島県南会津郡只見町只見:只見地区センターにおいて奥会津大学の講座があり、菅家がお話しします。2010年秋より開講したもので只見川電源流域振興協議会(事務局・三島町役場内)主催。
講座は昭和村下中津川 役場前の生活改善センター 一階のNPO苧麻倶楽部が担当している。→ 講座風景
■
■ 「奥会津の地域の調べ方」 昭和村大岐・菅家博昭 撰
1.調べる・歩く・見る・聴く・まとめる・残す・伝える
集落(ムラ)の歴史・地誌・記憶→ 字誌(あざし)、大字誌
渡辺満『集落誌せきざわ』(1988年) 耶麻郡山都町三津合字諏訪
2.文献調査 (書かれていない事も存在する)
(1)地図類
各自治体は1万分の1(分割)、2万5千分の1、5万分の1の地図を所持している。それを入手し該当集落を拡大コピーしておく。
または国土地理院の地形図2万5千分の1
地図閲覧サービス http://watchizu.gsi.go.jp/
(2)空中写真 1970年代
http://archive.gsi.go.jp/airphoto/search.html
(3)遺跡等(旧石器・縄文・弥生・古代・中世城館跡)
福島県文化財センター白河館まほろん http://www.mahoron.fks.ed.jp/search.html
(4)奥会津の自治体史誌
三島町史 昭和43年
柳津町史 全2巻(総説編・集落編)昭和49~52年
金山町史(上下民俗)昭和49年・51年 金山史談
図説会津只見の歴史 昭和43年
只見町史 全6巻・資料集5冊・文化財調査報告書14
南郷村史 全5巻・別巻1冊 昭和58~62年)
伊南村史 全7巻、編纂中
舘岩村史 全5巻(平成1~13年)
檜枝岐村史 昭和45年
昭和村の歴史 昭和48年
田島町史 全10巻・11冊(昭和52~平成3年)南山御蔵入について記述多い
福島県史、大沼郡誌、南会津郡案内誌(渡部円蔵・夢庵)
会津若松史、ビジュアル市史25巻等
『会津若松史研究 第十一号』(2010年)に会津若松市立図書館館長で市史編さん兼務の野口信一氏は、第三次会津若松市史編さん事業の終了について巻末に「資料の保存継承は我々の責務であり、規模は縮小されても資料の収集、整理、研究は残していく必要がある」としている。会津若松市では明治時代から大正時代にまとめられ昭和16、17年に『若松市史』上下巻が刊行された。その編さんのための資料は会津図書館に残されたという。二次は『会津若松史』は昭和37年から編さんがはじまり昭和39年から42年まで13冊が刊行された。しかし、資料は東北大学に委託したようなかたちで資料を預けたため会津若松市に資料が残されなかった、という。当時は通史主体の編さん方法で、資料編も原資料の抜粋だけで体系的な資料の掲載ではない。その後、自治体史の編さん方法も大きく変わり、まず資料を広く収集、調査分析し時代順による資料編を刊行、それを受け最後に通史の刊行と変化してきた。また現在では資料編が通史編よりも巻数的に多いものが主流になっている。新たな事実の解明により、通史は常に書き換えられる運命にあるから資料編が重要になっている。反省を踏まえ、史料の収集に力を入れた。史料所在調査、借用収集、整理、複写を経て史料目録原稿の作成、資料目録の出版。史料の保存・継承も重要で、原本は1種毎に所定の封筒に入れ所蔵者に返却、複写物を市史編さん室で永久保存して利用する。また貴重な資料については解読筆耕し、史料集として出版する、と紹介している。
(5)新編会津風土記
新編会津風土記(しんぺんあいづふどき)は、会津藩官選による会津藩領に関する地誌。全120巻。1803年(享和3年)から1809年(文化6年)にかけて編纂され、江戸幕府に上進された。界域、山川、原野、土産、関梁、水利、郡署、倉廩、神社、寺院、墳墓、古蹟、釈門、人物、旧家、褒善の16部門にわたり記述されている。
江戸幕府の地誌編纂事業のモデル的役割を果たすものとして編纂された地誌であると同時に、江戸時代における日本の地誌の代表とされる。(ウィキペディアより)。
復刻本は、会津若松市の歴史春秋社より全5巻
(6)報告書類
只見町教委『会津只見の中世城館跡』1995年
各町村教委、福島県等からの報告書、博物館研究紀要
各町村の民俗資料館等
(7)木地屋関係
近世木地屋の本拠小椋谷は現在滋賀県東近江市。資料としては杉本壽・橋本鉄男両氏による資料が著名であるが、『永源寺町史』全4巻がとてもよくまとめらている。平成18年に刊行された『永源寺町史 通史編』には生嶋輝美氏が593ページから658ページに蛭谷・君ヶ畑の木地師支配でまとめている。
江戸時代から明治初期に木地屋集落を全国巡廻してあるいた氏子かり帳については『永源寺町史』は2冊にわたり記載しており、最新のものである。会津地方の木地屋についてはふるく山口弥一郎氏の論考もある。また木地屋が農業をはじめ定着化することについては野本寛一先生も会津の北部の報告をまとめている(「木地師終焉地」『民俗文化第11号』1999年)。現在『永源寺町史』全4巻は「日本の古本屋」等で2万円程度で入手できる。木地制度についてよくまとめられており、これをまず読み、『木地語り』『木地師の跡を尋ねて』や各自治体史(市町村史)にてあたられると良い。研究史については田畑久夫『木地屋集落 系譜と変遷』(古今書院、2002年)
南会津町の奥会津博物館と2010年に改称したが、平成13年(2001)福島県田島町教育委員会『木地語り 企画展報告書』は下郷町在住の金井晃さんの執筆。同館で販売している。奥会津を中心とした会津地方の木地屋についてよくまとめられている。
昭和52年(1977)『福島の民俗』第5号に、昭和村中向の春日神社神主・菊地成彦先生は「奥会津の木地師」を投稿している。15ページから20ページ。度々木地屋を訪れて、すすけた火棚の上から、麻糸を十文字にからげた古文書入りの木箱を渡された時の感激は忘れられない、と木賊平木地を紹介。この文書は杉本壽氏も過去に紹介していると菊地先生は書いている。
1982年に発刊された南会津郡『田島町史』第6巻(下)近世資料Ⅱ。235ページから265ページまで木地屋資料が掲載されている。そのほとんどが昭和村のものだ(資料番号134から171まで)。当時の金山谷野尻組小野川村の大乗寺が旦那寺として機能しているのがわかる。平成14年(2002)に奥会津・昭和村教育委員会より出版された『木地師の跡を尋ねて』は佐倉の馬場勇五さんが編著。この木賊平木地の「飛び」の経路が詳細に再掲されている。本書はからむし工芸博物館・からむし織りの里で販売。
3.聞き書き
話者名・生年月日。公表するときは同意を得る。
聞きたいことを聞くのではなく、話したいことを受ける。
4.まとめ方事例
白日社・志村俊司さんによる檜枝岐等の聞き書きが秀逸である。
平野惣吉 述『山人の賦 Ⅰ』(1984年)尾瀬・奥只見の猟師とケモノたち
平野輿三郎 述『 同 Ⅱ』(1985年)尾瀬に生きた最後の猟師
平野福朔・勘三郎『 同 Ⅲ』(1988年)檜枝岐・山に生きる
---
トチハカリ
鈴木克彦「昭和村松山物語 2005年 聞書から」(『福島県立博物館紀要』第20号、2006年)で、奥会津・昭和村大字松山字居平の栗城八郎さん(昭和七年生まれ)は「ブナの森について」で以下のように語っているのが鈴木克彦さんにより採録されている。
昔は、松山でも近くにブナの大木がいっぺえあったが、みんな切っちまった。今は、白沢のずうーと奥に行かねえどブナ林はねえな。近くまでブナの大木が生えでだ頃(昭和25,6年頃まで)は、クマゲラど言って、体は黒くて、頭が赤いキツツキがいただ。いまはゼンメエ採りに行っても、キノコ採りに行っても、まるっきり見かけなぐなっちまった。クマゲラなんかは、鉄砲で撃つ人なんのは、いねがったな。せえがら、山さ行くど、遠くまで聞こえるように「カラカラカラカラ」って音がするこどあっぺ。穴の内側でコココココって首振る時の音なんだ。俺もじいーと、その様子をみてだごどあんだがな、野郎はコココココってやった後、暫く、聞き耳立ててんだっけ。したがら、俺は、木の中に虫がいっかどうだが、音で調べでんだど思うだ。せえがら、あの音聞くってえど、「トチハカリ(栃計り)だ」って、みんなよく言ってだなあ。それは、ちょうど、よく乾かした栃の実を、一升枡から空けるときの音に似ているから、そだごど言うんだど思う。
----
ウメハカリ
滋賀県民俗学会『愛知川谷の民俗 滋賀県神崎郡永源寺町』(1967年)の126ページの動物譚には以下のようにある。話者は伝承者左近治之助。
うめはかり(けらこの1種という) 梅の実を板の間に転がした時の音のような鳴き方をする。
わし 明治時代にはよく見かけたが最近は余り見ない。
ほととぎす たくさんいる
かっこう たくさんいる
まめどり(つつどり) むかしお婆さんが豆を竹の筒に入れて保存していたが、使おうとしたときにその置いた場所を忘れてしまい困っていたときに、この鳥が来て「ツツ・ツー」と鳴いて教えたのでお婆さんは思い出し、以後この鳥をまめどりと呼ぶようになったという昔話がある。
■
講座は昭和村下中津川 役場前の生活改善センター 一階のNPO苧麻倶楽部が担当している。→ 講座風景
■
■ 「奥会津の地域の調べ方」 昭和村大岐・菅家博昭 撰
1.調べる・歩く・見る・聴く・まとめる・残す・伝える
集落(ムラ)の歴史・地誌・記憶→ 字誌(あざし)、大字誌
渡辺満『集落誌せきざわ』(1988年) 耶麻郡山都町三津合字諏訪
2.文献調査 (書かれていない事も存在する)
(1)地図類
各自治体は1万分の1(分割)、2万5千分の1、5万分の1の地図を所持している。それを入手し該当集落を拡大コピーしておく。
または国土地理院の地形図2万5千分の1
地図閲覧サービス http://watchizu.gsi.go.jp/
(2)空中写真 1970年代
http://archive.gsi.go.jp/airphoto/search.html
(3)遺跡等(旧石器・縄文・弥生・古代・中世城館跡)
福島県文化財センター白河館まほろん http://www.mahoron.fks.ed.jp/search.html
(4)奥会津の自治体史誌
三島町史 昭和43年
柳津町史 全2巻(総説編・集落編)昭和49~52年
金山町史(上下民俗)昭和49年・51年 金山史談
図説会津只見の歴史 昭和43年
只見町史 全6巻・資料集5冊・文化財調査報告書14
南郷村史 全5巻・別巻1冊 昭和58~62年)
伊南村史 全7巻、編纂中
舘岩村史 全5巻(平成1~13年)
檜枝岐村史 昭和45年
昭和村の歴史 昭和48年
田島町史 全10巻・11冊(昭和52~平成3年)南山御蔵入について記述多い
福島県史、大沼郡誌、南会津郡案内誌(渡部円蔵・夢庵)
会津若松史、ビジュアル市史25巻等
『会津若松史研究 第十一号』(2010年)に会津若松市立図書館館長で市史編さん兼務の野口信一氏は、第三次会津若松市史編さん事業の終了について巻末に「資料の保存継承は我々の責務であり、規模は縮小されても資料の収集、整理、研究は残していく必要がある」としている。会津若松市では明治時代から大正時代にまとめられ昭和16、17年に『若松市史』上下巻が刊行された。その編さんのための資料は会津図書館に残されたという。二次は『会津若松史』は昭和37年から編さんがはじまり昭和39年から42年まで13冊が刊行された。しかし、資料は東北大学に委託したようなかたちで資料を預けたため会津若松市に資料が残されなかった、という。当時は通史主体の編さん方法で、資料編も原資料の抜粋だけで体系的な資料の掲載ではない。その後、自治体史の編さん方法も大きく変わり、まず資料を広く収集、調査分析し時代順による資料編を刊行、それを受け最後に通史の刊行と変化してきた。また現在では資料編が通史編よりも巻数的に多いものが主流になっている。新たな事実の解明により、通史は常に書き換えられる運命にあるから資料編が重要になっている。反省を踏まえ、史料の収集に力を入れた。史料所在調査、借用収集、整理、複写を経て史料目録原稿の作成、資料目録の出版。史料の保存・継承も重要で、原本は1種毎に所定の封筒に入れ所蔵者に返却、複写物を市史編さん室で永久保存して利用する。また貴重な資料については解読筆耕し、史料集として出版する、と紹介している。
(5)新編会津風土記
新編会津風土記(しんぺんあいづふどき)は、会津藩官選による会津藩領に関する地誌。全120巻。1803年(享和3年)から1809年(文化6年)にかけて編纂され、江戸幕府に上進された。界域、山川、原野、土産、関梁、水利、郡署、倉廩、神社、寺院、墳墓、古蹟、釈門、人物、旧家、褒善の16部門にわたり記述されている。
江戸幕府の地誌編纂事業のモデル的役割を果たすものとして編纂された地誌であると同時に、江戸時代における日本の地誌の代表とされる。(ウィキペディアより)。
復刻本は、会津若松市の歴史春秋社より全5巻
(6)報告書類
只見町教委『会津只見の中世城館跡』1995年
各町村教委、福島県等からの報告書、博物館研究紀要
各町村の民俗資料館等
(7)木地屋関係
近世木地屋の本拠小椋谷は現在滋賀県東近江市。資料としては杉本壽・橋本鉄男両氏による資料が著名であるが、『永源寺町史』全4巻がとてもよくまとめらている。平成18年に刊行された『永源寺町史 通史編』には生嶋輝美氏が593ページから658ページに蛭谷・君ヶ畑の木地師支配でまとめている。
江戸時代から明治初期に木地屋集落を全国巡廻してあるいた氏子かり帳については『永源寺町史』は2冊にわたり記載しており、最新のものである。会津地方の木地屋についてはふるく山口弥一郎氏の論考もある。また木地屋が農業をはじめ定着化することについては野本寛一先生も会津の北部の報告をまとめている(「木地師終焉地」『民俗文化第11号』1999年)。現在『永源寺町史』全4巻は「日本の古本屋」等で2万円程度で入手できる。木地制度についてよくまとめられており、これをまず読み、『木地語り』『木地師の跡を尋ねて』や各自治体史(市町村史)にてあたられると良い。研究史については田畑久夫『木地屋集落 系譜と変遷』(古今書院、2002年)
南会津町の奥会津博物館と2010年に改称したが、平成13年(2001)福島県田島町教育委員会『木地語り 企画展報告書』は下郷町在住の金井晃さんの執筆。同館で販売している。奥会津を中心とした会津地方の木地屋についてよくまとめられている。
昭和52年(1977)『福島の民俗』第5号に、昭和村中向の春日神社神主・菊地成彦先生は「奥会津の木地師」を投稿している。15ページから20ページ。度々木地屋を訪れて、すすけた火棚の上から、麻糸を十文字にからげた古文書入りの木箱を渡された時の感激は忘れられない、と木賊平木地を紹介。この文書は杉本壽氏も過去に紹介していると菊地先生は書いている。
1982年に発刊された南会津郡『田島町史』第6巻(下)近世資料Ⅱ。235ページから265ページまで木地屋資料が掲載されている。そのほとんどが昭和村のものだ(資料番号134から171まで)。当時の金山谷野尻組小野川村の大乗寺が旦那寺として機能しているのがわかる。平成14年(2002)に奥会津・昭和村教育委員会より出版された『木地師の跡を尋ねて』は佐倉の馬場勇五さんが編著。この木賊平木地の「飛び」の経路が詳細に再掲されている。本書はからむし工芸博物館・からむし織りの里で販売。
3.聞き書き
話者名・生年月日。公表するときは同意を得る。
聞きたいことを聞くのではなく、話したいことを受ける。
4.まとめ方事例
白日社・志村俊司さんによる檜枝岐等の聞き書きが秀逸である。
平野惣吉 述『山人の賦 Ⅰ』(1984年)尾瀬・奥只見の猟師とケモノたち
平野輿三郎 述『 同 Ⅱ』(1985年)尾瀬に生きた最後の猟師
平野福朔・勘三郎『 同 Ⅲ』(1988年)檜枝岐・山に生きる
---
トチハカリ
鈴木克彦「昭和村松山物語 2005年 聞書から」(『福島県立博物館紀要』第20号、2006年)で、奥会津・昭和村大字松山字居平の栗城八郎さん(昭和七年生まれ)は「ブナの森について」で以下のように語っているのが鈴木克彦さんにより採録されている。
昔は、松山でも近くにブナの大木がいっぺえあったが、みんな切っちまった。今は、白沢のずうーと奥に行かねえどブナ林はねえな。近くまでブナの大木が生えでだ頃(昭和25,6年頃まで)は、クマゲラど言って、体は黒くて、頭が赤いキツツキがいただ。いまはゼンメエ採りに行っても、キノコ採りに行っても、まるっきり見かけなぐなっちまった。クマゲラなんかは、鉄砲で撃つ人なんのは、いねがったな。せえがら、山さ行くど、遠くまで聞こえるように「カラカラカラカラ」って音がするこどあっぺ。穴の内側でコココココって首振る時の音なんだ。俺もじいーと、その様子をみてだごどあんだがな、野郎はコココココってやった後、暫く、聞き耳立ててんだっけ。したがら、俺は、木の中に虫がいっかどうだが、音で調べでんだど思うだ。せえがら、あの音聞くってえど、「トチハカリ(栃計り)だ」って、みんなよく言ってだなあ。それは、ちょうど、よく乾かした栃の実を、一升枡から空けるときの音に似ているから、そだごど言うんだど思う。
----
ウメハカリ
滋賀県民俗学会『愛知川谷の民俗 滋賀県神崎郡永源寺町』(1967年)の126ページの動物譚には以下のようにある。話者は伝承者左近治之助。
うめはかり(けらこの1種という) 梅の実を板の間に転がした時の音のような鳴き方をする。
わし 明治時代にはよく見かけたが最近は余り見ない。
ほととぎす たくさんいる
かっこう たくさんいる
まめどり(つつどり) むかしお婆さんが豆を竹の筒に入れて保存していたが、使おうとしたときにその置いた場所を忘れてしまい困っていたときに、この鳥が来て「ツツ・ツー」と鳴いて教えたのでお婆さんは思い出し、以後この鳥をまめどりと呼ぶようになったという昔話がある。
■
2010年11月21日日曜日
雑誌:会津学 6号 発刊集会
■2010年11月21日(日)13時より17時まで、福島県三島町西方の西隆寺にて開催された。奥会津は晴れの一日。20余名の参加者があった。進行は川合氏。
執筆者の一人、斎藤民部先生が小学4年生の授業を通じての地域の調べ方を説明された。30年前に実践したことのふり返りである。80歳になられ、聴覚に障害があるため参加者からの質問は筆談で行い、斎藤先生は口頭で回答された。
■その後、参加者のなかで執筆者に今回の記事の聞き書きのなかでの課題などを報告していただき、雑誌内に取り上げられた内容を話し合った。また赤坂憲雄さんにも感想をうかがった。
■会津学研究会員ら参加者でその後、懇親会を20時まで行い散会した。
執筆者の一人、斎藤民部先生が小学4年生の授業を通じての地域の調べ方を説明された。30年前に実践したことのふり返りである。80歳になられ、聴覚に障害があるため参加者からの質問は筆談で行い、斎藤先生は口頭で回答された。
■その後、参加者のなかで執筆者に今回の記事の聞き書きのなかでの課題などを報告していただき、雑誌内に取り上げられた内容を話し合った。また赤坂憲雄さんにも感想をうかがった。
■会津学研究会員ら参加者でその後、懇親会を20時まで行い散会した。
2010年11月17日水曜日
会津学 6号 発刊しました
■雑誌『会津学6号』は、11月14日頃に印刷。
昭和村からむし工芸博物館・三島町道の駅・JR会津川口駅売店・川口阿部書店・会津若松市駅前岩瀬書店等に配本され、11月18日頃まで店頭に並ぶ予定です。1500円。奥会津書房刊
■11月21日(日)13時より、福島県大沼郡三島町西方字巣郷4684・西隆寺で『会津学6号』発刊の記念の会を開催します。会津学研究会・奥会津書房主催。本も販売いたします。赤坂憲雄さんも参加される予定です。
昭和村からむし工芸博物館・三島町道の駅・JR会津川口駅売店・川口阿部書店・会津若松市駅前岩瀬書店等に配本され、11月18日頃まで店頭に並ぶ予定です。1500円。奥会津書房刊
■11月21日(日)13時より、福島県大沼郡三島町西方字巣郷4684・西隆寺で『会津学6号』発刊の記念の会を開催します。会津学研究会・奥会津書房主催。本も販売いたします。赤坂憲雄さんも参加される予定です。
2010年10月15日金曜日
カラムシを支えるコガヤ(カリヤス)
カラムシ栽培におけるコガヤ(カリヤス)の重要性
菅家博昭
ボーガヤ(植物和名ススキ)とコガヤ(植物和名カリヤス)。形状は似ているが、異なる植物として認識され福島県奥会津の昭和村では古くからそれぞれに暮らしのなかにおいて利用されてきた。
イネ科のススキ属Miscanthus Anderssonには3種類ある。ススキMiscanthus sinensis Andersson、オギMiscanthus sacchariflorus、カリヤスMiscanthus tinctorius。いずれも昭和村で現在も生育が確認されている。
特にカリヤスは岐阜県富山県を中心とする中部山地に分布は濃く、東北地方南部までが分布域である。ススキに比べ桿が細く刈りやすく、合掌作りの屋根に、ススキ(大萱)とともにカリヤス(小萱)も使われる。その理由はススキよりも長持ちする、という。富山県五箇荘ではカリヤスが屋根材に使われているが、近年身近なススキから、かつての屋根材カリヤスを要望する事例が茅葺き保存家屋の改修時に、出て来ている(※1)。
カリヤスは、昭和村ではコガヤと呼ばれている。ススキはボーガヤである。ボーガヤは棒茅の意だと思われ昭和村域では使用されているが大茅と呼ぶ地域も隣接の柳津町冑中等にはある。中部山岳地域も大茅・小茅と呼んでいる。異なる植物として、明確に分けている。
昭和村で「カヤバ(カヤカリバ)」とは、共有利用を前提として採取制限(禁止)を持ち、春の山焼きが行われ、秋彼岸以降に、やまのくちあけ(山の口、鎌揃え)で開放・採取開始する、コガヤ(カリヤス)を刈る半自然草地のことである。これらは第2次大戦前後まで昭和村内の全域(各集落)で、行われていた。集落を取り囲む山塊のなかに複数設置されている。
カヤバの春の山焼きは、残雪が尾根筋に残る時期に前年の草類が乾燥して燃えやすい時期に、斜面下方から火を点火し、そのままに放置するもので「くっつげはなし」(松山 ※2)とよばれていた。火は消さず自然鎮火を待つため数日から1週間も燃え、時に尾根を越えて隣村の山まで焼けたことがある、という(大芦)。
コガヤを刈る時期は旧暦の秋彼岸後で、水田での稲刈り等との関係で採取(刈り取り)時期が集落毎に決められていた。すでに立ち枯れし乾燥が進んでいることもあるが、3把(は、束)で立てさらに3把重ねての6把立が多く、それで乾燥させる。カヤマキ、カヤボッチはタテ(立)で数える。乾燥後、それを集落に運搬した。
晩秋、集落のなかの家屋(母屋)外壁にはコガヤを2段、3段に巻き、フユガキ(冬囲い・雪囲い)とした。春先に飼育動物(馬牛等)の餌が無くなると、このフユガキを外して与えることもあった。土蔵等にはボーガヤ(ススキ)をフユガキとして、これは外しながら木炭を入れるスゴを編んだ(大岐)。
これまで現代語訳の筆耕が存在していたが、喜多方市立図書館蔵で、喜多方市教育委員会の協力でその原本がはじめて今回の「からむし畑」展の事前調査で確認された。安政五年(1858)に松山村(現在の昭和村大字松山)の佐々木志摩之助が書いた「青苧仕法書上」という近世江戸時代のカラムシ栽培の手引き書で、ほぼ現在に伝わる内容と同じであることを証左している。特に秋にカヤを刈り、家の冬囲いとし来春そのカヤでカラムシ(青苧)を焼くということも明記されている。
フユガキのコガヤは、カラムシ畑に運ばれ、焼き草として畑に散らし(掛けて)焼かれる。焼畑のときの、コガヤの火力がカラムシの芽を揃える、品質確保のためには必要なものであったようだ。コガヤでなければならない理由の今後の聞き取り調査が待たれる。カラムシ畑を焼くには、ボーガヤだと火力が強い、あるいは太くて燃えないなどの問題がある(小中津川)。
2010年9月17日(金)雨の午前、昭和村小中津川の柳沢で、本名初好さん(昭和13年生)が茅刈りをしていたので、話をうかがった。四畝歩のカラムシ畑を春に焼くためのカヤ(ススキ)の調達をしている。コガヤ(カリヤス)は少なくなり、ボーガヤ(ススキ)を刈っている。左手で三つかみで1束とし1把(いっぱ)。それを3把で立てて、上に3把を重ねる。1立(ひとたて)は6把(ろっぱ)立て。これを30立(たて)、昨年(2009年)秋に刈って乾燥させ、翌春(つまりこの春5月)に、焼草とした。茎が太いと燃えないから根本から50cmくらいは切り捨て、残った上部のみ使っているという。
4畝(アール・a)のカラムシ焼に必要なカヤは、30立て。180把である、ということが明らかになった。本来はコガヤ(植物和名カリヤス)が良いがいまは少ない。
さて、カヤバの管理は、どのようにしたのか?といえば、「秋にコガヤを刈るときに手入れした」といい、その内容は「生えてきた樹木を根本から切り、不要な草類も刈り、そこに置いた」という管理であった(大岐)。
「コガヤはカヤバの周囲の樹木が育ち日陰になると消え」「ボーガヤに負けて株が無くなる」という。「肥えた土地にはボーガヤが育ち、やせた硬い土のところにはコガヤが育つ」といい「コガヤのカヤバにはシメジもよく出る」という(大岐)。カヤバは春の山菜であるワラビも多く出、また夏の盆にはボンバナと称するオミナエシ、ワレモコウ、キキョウなどの野の花が採取され仏前・墓前に手向けられた。
昭和村における草の利用は馬の飼育のための秣(まぐさ)、いわゆる朝草刈り、冬の飼育飼料としてのカッタテ・カッポシ(乾燥草)を草のショウ(生)が抜ける前の秋彼岸前に刈る。そして屋根材のボーガヤ確保、フユガキとカラムシ焼き・屋根の補修のサシガヤとしてのコガヤの刈り取り、、、と目的に応じた草の確保、半自然草地の維持管理が行われていた。しかしその具体的な内実はしられていない。稲刈り後、稲束をネリ(稲架)で乾燥する。その際の最上段は「カサイネ(笠稲)」と呼び、湿気が最後まで抜けないため別に管理する。このカサイネをカラムシ畑のほとりに運ぶ(カサワラ)。カラムシ焼き畑後に散らすしきわらとして湿気具合、風で飛ばないなど使いやすいのだ、という(大岐、大芦)。
昭和村におけるカラムシ栽培・青苧生産については、それを支える広大なカヤバ(カリヤス草地)の存在。植物、特に多用な草ヒロロ(ミヤマカンスゲ)や蔓のマタタビ、モワダ(シナ)等樹皮を維持管理し、それを生活の中で活用してきた。その基層文化、生活技術、自然認識のうえに、カラムシ栽培・生産が形成されている。カラムシ単独では持続はあり得ず、その全体像を明らかにすることと、カラムシにつながる生活技術を復権するひとつの試みとして、たとえば遊休農地等にコガヤ(カリヤス)を生産する小茅畑の復活が待たれる。
また近年、減農薬農業を政府が推進しているが、そのなかの技術にバンカープランツがある。目的とする植物(野菜等)の園地をトウモロコシ等の背の高い植物等で帯状に周囲を取り囲む。このことで囲う植物帯で侵入する昆虫等を遮蔽し、あるいは遮蔽帯に小さな生態系を作り、この囲い植物帯から園地に益虫を供給する、という農法。これはかつて昭和村域でアサとカラムシの栽培が行われていた時代の、カラムシ畑をアサで囲む技法に似ている。風除けとしてのアサの利用であるが、昆虫への対応など、このような伝統技術の現代的解明も今後必要になっている。「ウセクチ」のカラムシ畑にアサを蒔く、という連作障害回避技術解明も含めて、現在の「からむし畑」の技術解明課題は多い。カラムシ生産など伝統農法が内包している哲学的認識、伝統農法技術の科学的解明は、第三世界の支援に援用されるだけでなく、日本の山間地域の基層文化の再生を通し次世代の成熟のために必要となってくると思われる。(かんけひろあき 昭和村大岐在住、会津学研究会代表)
-----
(※1)2010年10月7日、大芦家で開催された会津学研究会主催「コガヤに学ぶ」で報告した柏春菜さん「地域毎の半自然草地維持の仕組みとそのバックグラウンドについて」(岐阜県立森林文化アカデミー森と木のクリエーター科里山研究会)による。
(※2) 『福島県立博物館紀要』第20号(2006年)に、鈴木克彦さんが「昭和村松山物語~2005年の聞書から」を報告している。このなかで「くっつげ放(はな)し」(87ページ)、「カッチギ(刈敷)」「カッポシ(刈り干し)」(92ページ)についての記載がある。カッチギについては雑木の枝を切り積み翌年使用する、とある。
菅家博昭
ボーガヤ(植物和名ススキ)とコガヤ(植物和名カリヤス)。形状は似ているが、異なる植物として認識され福島県奥会津の昭和村では古くからそれぞれに暮らしのなかにおいて利用されてきた。
イネ科のススキ属Miscanthus Anderssonには3種類ある。ススキMiscanthus sinensis Andersson、オギMiscanthus sacchariflorus、カリヤスMiscanthus tinctorius。いずれも昭和村で現在も生育が確認されている。
特にカリヤスは岐阜県富山県を中心とする中部山地に分布は濃く、東北地方南部までが分布域である。ススキに比べ桿が細く刈りやすく、合掌作りの屋根に、ススキ(大萱)とともにカリヤス(小萱)も使われる。その理由はススキよりも長持ちする、という。富山県五箇荘ではカリヤスが屋根材に使われているが、近年身近なススキから、かつての屋根材カリヤスを要望する事例が茅葺き保存家屋の改修時に、出て来ている(※1)。
カリヤスは、昭和村ではコガヤと呼ばれている。ススキはボーガヤである。ボーガヤは棒茅の意だと思われ昭和村域では使用されているが大茅と呼ぶ地域も隣接の柳津町冑中等にはある。中部山岳地域も大茅・小茅と呼んでいる。異なる植物として、明確に分けている。
昭和村で「カヤバ(カヤカリバ)」とは、共有利用を前提として採取制限(禁止)を持ち、春の山焼きが行われ、秋彼岸以降に、やまのくちあけ(山の口、鎌揃え)で開放・採取開始する、コガヤ(カリヤス)を刈る半自然草地のことである。これらは第2次大戦前後まで昭和村内の全域(各集落)で、行われていた。集落を取り囲む山塊のなかに複数設置されている。
カヤバの春の山焼きは、残雪が尾根筋に残る時期に前年の草類が乾燥して燃えやすい時期に、斜面下方から火を点火し、そのままに放置するもので「くっつげはなし」(松山 ※2)とよばれていた。火は消さず自然鎮火を待つため数日から1週間も燃え、時に尾根を越えて隣村の山まで焼けたことがある、という(大芦)。
コガヤを刈る時期は旧暦の秋彼岸後で、水田での稲刈り等との関係で採取(刈り取り)時期が集落毎に決められていた。すでに立ち枯れし乾燥が進んでいることもあるが、3把(は、束)で立てさらに3把重ねての6把立が多く、それで乾燥させる。カヤマキ、カヤボッチはタテ(立)で数える。乾燥後、それを集落に運搬した。
晩秋、集落のなかの家屋(母屋)外壁にはコガヤを2段、3段に巻き、フユガキ(冬囲い・雪囲い)とした。春先に飼育動物(馬牛等)の餌が無くなると、このフユガキを外して与えることもあった。土蔵等にはボーガヤ(ススキ)をフユガキとして、これは外しながら木炭を入れるスゴを編んだ(大岐)。
これまで現代語訳の筆耕が存在していたが、喜多方市立図書館蔵で、喜多方市教育委員会の協力でその原本がはじめて今回の「からむし畑」展の事前調査で確認された。安政五年(1858)に松山村(現在の昭和村大字松山)の佐々木志摩之助が書いた「青苧仕法書上」という近世江戸時代のカラムシ栽培の手引き書で、ほぼ現在に伝わる内容と同じであることを証左している。特に秋にカヤを刈り、家の冬囲いとし来春そのカヤでカラムシ(青苧)を焼くということも明記されている。
フユガキのコガヤは、カラムシ畑に運ばれ、焼き草として畑に散らし(掛けて)焼かれる。焼畑のときの、コガヤの火力がカラムシの芽を揃える、品質確保のためには必要なものであったようだ。コガヤでなければならない理由の今後の聞き取り調査が待たれる。カラムシ畑を焼くには、ボーガヤだと火力が強い、あるいは太くて燃えないなどの問題がある(小中津川)。
2010年9月17日(金)雨の午前、昭和村小中津川の柳沢で、本名初好さん(昭和13年生)が茅刈りをしていたので、話をうかがった。四畝歩のカラムシ畑を春に焼くためのカヤ(ススキ)の調達をしている。コガヤ(カリヤス)は少なくなり、ボーガヤ(ススキ)を刈っている。左手で三つかみで1束とし1把(いっぱ)。それを3把で立てて、上に3把を重ねる。1立(ひとたて)は6把(ろっぱ)立て。これを30立(たて)、昨年(2009年)秋に刈って乾燥させ、翌春(つまりこの春5月)に、焼草とした。茎が太いと燃えないから根本から50cmくらいは切り捨て、残った上部のみ使っているという。
4畝(アール・a)のカラムシ焼に必要なカヤは、30立て。180把である、ということが明らかになった。本来はコガヤ(植物和名カリヤス)が良いがいまは少ない。
さて、カヤバの管理は、どのようにしたのか?といえば、「秋にコガヤを刈るときに手入れした」といい、その内容は「生えてきた樹木を根本から切り、不要な草類も刈り、そこに置いた」という管理であった(大岐)。
「コガヤはカヤバの周囲の樹木が育ち日陰になると消え」「ボーガヤに負けて株が無くなる」という。「肥えた土地にはボーガヤが育ち、やせた硬い土のところにはコガヤが育つ」といい「コガヤのカヤバにはシメジもよく出る」という(大岐)。カヤバは春の山菜であるワラビも多く出、また夏の盆にはボンバナと称するオミナエシ、ワレモコウ、キキョウなどの野の花が採取され仏前・墓前に手向けられた。
昭和村における草の利用は馬の飼育のための秣(まぐさ)、いわゆる朝草刈り、冬の飼育飼料としてのカッタテ・カッポシ(乾燥草)を草のショウ(生)が抜ける前の秋彼岸前に刈る。そして屋根材のボーガヤ確保、フユガキとカラムシ焼き・屋根の補修のサシガヤとしてのコガヤの刈り取り、、、と目的に応じた草の確保、半自然草地の維持管理が行われていた。しかしその具体的な内実はしられていない。稲刈り後、稲束をネリ(稲架)で乾燥する。その際の最上段は「カサイネ(笠稲)」と呼び、湿気が最後まで抜けないため別に管理する。このカサイネをカラムシ畑のほとりに運ぶ(カサワラ)。カラムシ焼き畑後に散らすしきわらとして湿気具合、風で飛ばないなど使いやすいのだ、という(大岐、大芦)。
昭和村におけるカラムシ栽培・青苧生産については、それを支える広大なカヤバ(カリヤス草地)の存在。植物、特に多用な草ヒロロ(ミヤマカンスゲ)や蔓のマタタビ、モワダ(シナ)等樹皮を維持管理し、それを生活の中で活用してきた。その基層文化、生活技術、自然認識のうえに、カラムシ栽培・生産が形成されている。カラムシ単独では持続はあり得ず、その全体像を明らかにすることと、カラムシにつながる生活技術を復権するひとつの試みとして、たとえば遊休農地等にコガヤ(カリヤス)を生産する小茅畑の復活が待たれる。
また近年、減農薬農業を政府が推進しているが、そのなかの技術にバンカープランツがある。目的とする植物(野菜等)の園地をトウモロコシ等の背の高い植物等で帯状に周囲を取り囲む。このことで囲う植物帯で侵入する昆虫等を遮蔽し、あるいは遮蔽帯に小さな生態系を作り、この囲い植物帯から園地に益虫を供給する、という農法。これはかつて昭和村域でアサとカラムシの栽培が行われていた時代の、カラムシ畑をアサで囲む技法に似ている。風除けとしてのアサの利用であるが、昆虫への対応など、このような伝統技術の現代的解明も今後必要になっている。「ウセクチ」のカラムシ畑にアサを蒔く、という連作障害回避技術解明も含めて、現在の「からむし畑」の技術解明課題は多い。カラムシ生産など伝統農法が内包している哲学的認識、伝統農法技術の科学的解明は、第三世界の支援に援用されるだけでなく、日本の山間地域の基層文化の再生を通し次世代の成熟のために必要となってくると思われる。(かんけひろあき 昭和村大岐在住、会津学研究会代表)
-----
(※1)2010年10月7日、大芦家で開催された会津学研究会主催「コガヤに学ぶ」で報告した柏春菜さん「地域毎の半自然草地維持の仕組みとそのバックグラウンドについて」(岐阜県立森林文化アカデミー森と木のクリエーター科里山研究会)による。
(※2) 『福島県立博物館紀要』第20号(2006年)に、鈴木克彦さんが「昭和村松山物語~2005年の聞書から」を報告している。このなかで「くっつげ放(はな)し」(87ページ)、「カッチギ(刈敷)」「カッポシ(刈り干し)」(92ページ)についての記載がある。カッチギについては雑木の枝を切り積み翌年使用する、とある。
カリヤス(コガヤ、小茅)
10月7日に開催した学習会。コガヤ(カリヤス)の認識が改まった。
■■10月7日(木)は19時より大芦家にて、会津学研究会の小さな学習会が行われた。昨年10月に奥会津に調査された富山県生まれの柏春菜さんの「地域毎の半自然草地維持の仕組みとそのバックグラウンドについて」である。
岐阜県立森林文化アカデミー森と木のクリエーター科里山研究会に所属し、今春春に卒業研究として発表した論文をもとに1時間、スライド映写(PPT)を使用して報告いただいた。富山県・岐阜県・長野県の4集落のカヤ(ススキとカリヤス)利用の聞き取りと植物相調査、当地昭和村大岐を加えた草の利用の考察が行われた。
昭和村での事例として、カラムシ生産を支える伝統的な基層技術として春のカラムシ焼き(焼畑)には、必ずコガヤ(植物和名カリヤス)を使用している。しかし最近はボーガヤ(植物和名ススキ)が繁茂しそれしか入手できない状況にある。集落の農業が衰退し、真っ先に森林内に維持されてきた「カヤカリバ(カヤバ、茅場)」の共有地(コモンズ)が森林に戻ってきて、あるいは杉やカラマツの造林、集落開拓等により焼失している。一方、耕作地域が柳やススキが繁茂しいわゆる耕作放棄地が野に戻っている。
コガヤの社会的役割を探ることと、今後のコガヤの復活を企図して今回の学習会は開催された。植物が支える社会、の構想の意味を考えた。
→ 千葉県一宮市から参加されたマツヤマさん
→ 村内からの参加者
→ 大芦家
→ 菅家博昭付板
■繊維植物を得るために畑に受け付けた宿根草のカラムシ(苧麻・青苧)の生産に、乾燥したコガヤ(カリヤス)が重要な意味を持っています。雪融け後の5月に出てくるカラムシの芽を揃えるために、畑にコガヤを散らして焼き、カラムシの発芽を揃え、ひいては均一な成長をうながすためには、細いコガヤが最適であることがわかっています。火入れといっても火力をどのように維持し、かつ均一に焼き、そして目的とする植物の品質を高めるか?というなかでコガヤを取得する草地(半自然草地)が、各集落ごとに、共有地(コモンズ)として近世江戸時代から維持されてきました。しかしコガヤ草地を維持する、という野へのはたらきかけの基層技術がなにひとつわかっていません。春の山焼き(つけっぱなし)、秋のやまのくちあけ(かまぞろえ)ぐらいでしょうか。今回の柏さんの報告を聞くと中部日本では夏に数度茅場(半自然草地)の他種植物の除去・掃除が行われています。その除去した草はまた別な用途に利用している、という姿がわかってきました。昭和村におけるカヤカリバ(茅場)は、屋根材のためのカヤ取得ではなく、冬囲いとして家屋を雪圧力から守り、その融雪後カラムシ畑に運ばれてカラムシの品質確保のために「焼畑」のために、使用されていました。
■10月23日に昭和村の隣村・南会津町舘岩地区水引で茅刈り体験会(ツアー)が行われます。 →山村再生塾
■初出記事 → 菅家(記憶の森を歩く10月7日) →10月8日
■■10月7日(木)は19時より大芦家にて、会津学研究会の小さな学習会が行われた。昨年10月に奥会津に調査された富山県生まれの柏春菜さんの「地域毎の半自然草地維持の仕組みとそのバックグラウンドについて」である。
岐阜県立森林文化アカデミー森と木のクリエーター科里山研究会に所属し、今春春に卒業研究として発表した論文をもとに1時間、スライド映写(PPT)を使用して報告いただいた。富山県・岐阜県・長野県の4集落のカヤ(ススキとカリヤス)利用の聞き取りと植物相調査、当地昭和村大岐を加えた草の利用の考察が行われた。
昭和村での事例として、カラムシ生産を支える伝統的な基層技術として春のカラムシ焼き(焼畑)には、必ずコガヤ(植物和名カリヤス)を使用している。しかし最近はボーガヤ(植物和名ススキ)が繁茂しそれしか入手できない状況にある。集落の農業が衰退し、真っ先に森林内に維持されてきた「カヤカリバ(カヤバ、茅場)」の共有地(コモンズ)が森林に戻ってきて、あるいは杉やカラマツの造林、集落開拓等により焼失している。一方、耕作地域が柳やススキが繁茂しいわゆる耕作放棄地が野に戻っている。
コガヤの社会的役割を探ることと、今後のコガヤの復活を企図して今回の学習会は開催された。植物が支える社会、の構想の意味を考えた。
→ 千葉県一宮市から参加されたマツヤマさん
→ 村内からの参加者
→ 大芦家
→ 菅家博昭付板
■繊維植物を得るために畑に受け付けた宿根草のカラムシ(苧麻・青苧)の生産に、乾燥したコガヤ(カリヤス)が重要な意味を持っています。雪融け後の5月に出てくるカラムシの芽を揃えるために、畑にコガヤを散らして焼き、カラムシの発芽を揃え、ひいては均一な成長をうながすためには、細いコガヤが最適であることがわかっています。火入れといっても火力をどのように維持し、かつ均一に焼き、そして目的とする植物の品質を高めるか?というなかでコガヤを取得する草地(半自然草地)が、各集落ごとに、共有地(コモンズ)として近世江戸時代から維持されてきました。しかしコガヤ草地を維持する、という野へのはたらきかけの基層技術がなにひとつわかっていません。春の山焼き(つけっぱなし)、秋のやまのくちあけ(かまぞろえ)ぐらいでしょうか。今回の柏さんの報告を聞くと中部日本では夏に数度茅場(半自然草地)の他種植物の除去・掃除が行われています。その除去した草はまた別な用途に利用している、という姿がわかってきました。昭和村におけるカヤカリバ(茅場)は、屋根材のためのカヤ取得ではなく、冬囲いとして家屋を雪圧力から守り、その融雪後カラムシ畑に運ばれてカラムシの品質確保のために「焼畑」のために、使用されていました。
■10月23日に昭和村の隣村・南会津町舘岩地区水引で茅刈り体験会(ツアー)が行われます。 →山村再生塾
■初出記事 → 菅家(記憶の森を歩く10月7日) →10月8日
登録:
投稿 (Atom)